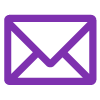北海道鳶土木工業組合 Union
【江戸消防】
|
|
消防組織としての火消は、江戸においては江戸幕府により、頻発する火事に対応する【防火・消火制度】として定められた。
町人によって組織されたものを町火消とよんだ。
江戸時代初期には火消の制度が定められておらず、度重なる大火を契機にまず武家火消が制度化され発達していった。
江戸時代中期に入ると、享保の改革によって町火消が制度化される。
そののち江戸時代後期から幕末にかけては、町火消が武家火消に代わって江戸の消防活動の中核を担うようになっていった。
江戸以外の大都市や各藩の城下町などでも、それぞれ火消の制度が定められていた。これらの消防組織は、明治維新後に廃止・改編されるが、その系譜は現代の消防署・消防団へと繋がっている。
消防組織の構成員としての火消は、火消人足ともいう。定火消の配下であった臥煙、町火消の中核をなした鳶人足(鳶職)などがあげられる。
組織ごとの対抗心や気性の荒さから、「加賀鳶と定火消の喧嘩」や「め組の喧嘩」などの騒動を起こすこともあった。
火消人足による消火の方法は、火事場周辺の建物を破壊し延焼を防ぐ破壊消防(除去消火法)が用いられ、明和年間ごろからは竜吐水(木製手押ポンプ)なども補助的に使用された。
|
【町火消】
町火消は、第8代将軍徳川吉宗の時代にはじまる町人による火消し。殆どが身体能力の高い鳶職で構成された。
各組の目印としてそれぞれ纏(まとい)と幟(のぼり)をつくらせた。
これらは混乱する火事場での目印にするという目的があったが、次第に各組を象徴するものとなっていった。
【纏と火事装束】
纏(まとい)は、江戸消防のシンボルであり、「纏が火を消した」と言われることすらあった。
町火消の盛装は、印半天、腹掛、股引などである。火事場へはさらに刺子頭巾(猫頭巾、目の部分だけが開いている)、膝下まである刺子長半天などを着て出動した。
半天の背中には組の紋が、えりには組名が染めつけられていた。刺子長半天には裏地に錦絵風の模様をつけた豪華なものもあった。
【釧路鳶土木工業組合】 年間行事
CONTENTS コンテンツ